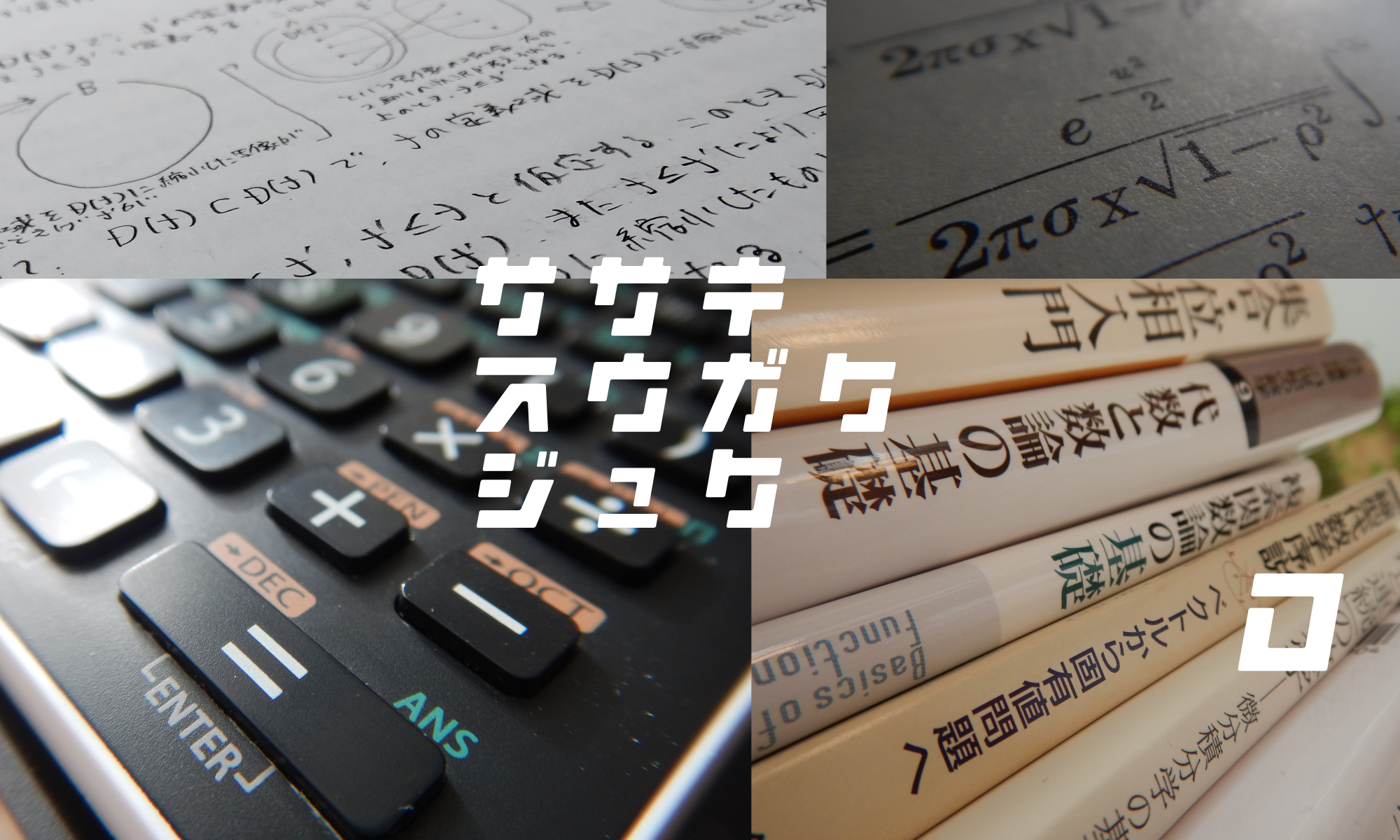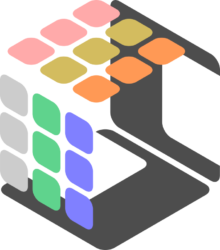\(p(x),~q(x)\)を条件とする.\(\forall\)は「任意記号(または全称記号)」と呼び,「任意の(Any),すべての(for All)」という意味です.Aをひっくり返して\(\forall\).このとき,
\[\forall x[p(x)\land q(x)]~\Longleftrightarrow \forall x p(x)\land \forall x q(x)\quad \cdots (\ast)\]
が成り立ちます.例えば,\(p(x)\)を「\(x\)は勉強が得意」という条件,\(q(x)\)を「\(x\)はスポーツが得意」という条件だとしましょう.このとき,\(\forall x[p(x)\land q(x)]\)は
\[\text{全員,勉強とスポーツ両方得意}\]
という意味になります.イメージし易さのため,\(x\in \text{(とあるクラス)}\)とすると,
\[\text{このクラスの全員が,勉強とスポーツ両方得意}\]
となります.いわば,スーパーマンみたいな奴だけで構成されたクラスですね,そんなクラスをイメージしてください.
他方,\(\forall x p(x)\land \forall x q(x)\)は\[\text{このクラスの全員が勉強が得意で,かつ,このクラスの全員がスポーツが得意}\]という意味になります.
これらの「翻訳」に従って,上の\((\ast)\)を記述し直してみると,
\begin{align*}
&\text{このクラスの全員が,勉強とスポーツ両方得意}\\
\Longleftrightarrow~&\text{このクラスの全員が勉強が得意で,かつ,このクラスの全員がスポーツが得意}
\end{align*}
ということになります.このようにイメージすると,\((\ast)\)の\(\Longleftarrow\)も\(\Longrightarrow\)もどちらも成り立つこと,すなわち同値であることが容易に納得できます.
注意:ただし,任意記号はまたは(\(\lor\))に関しては分配できません!